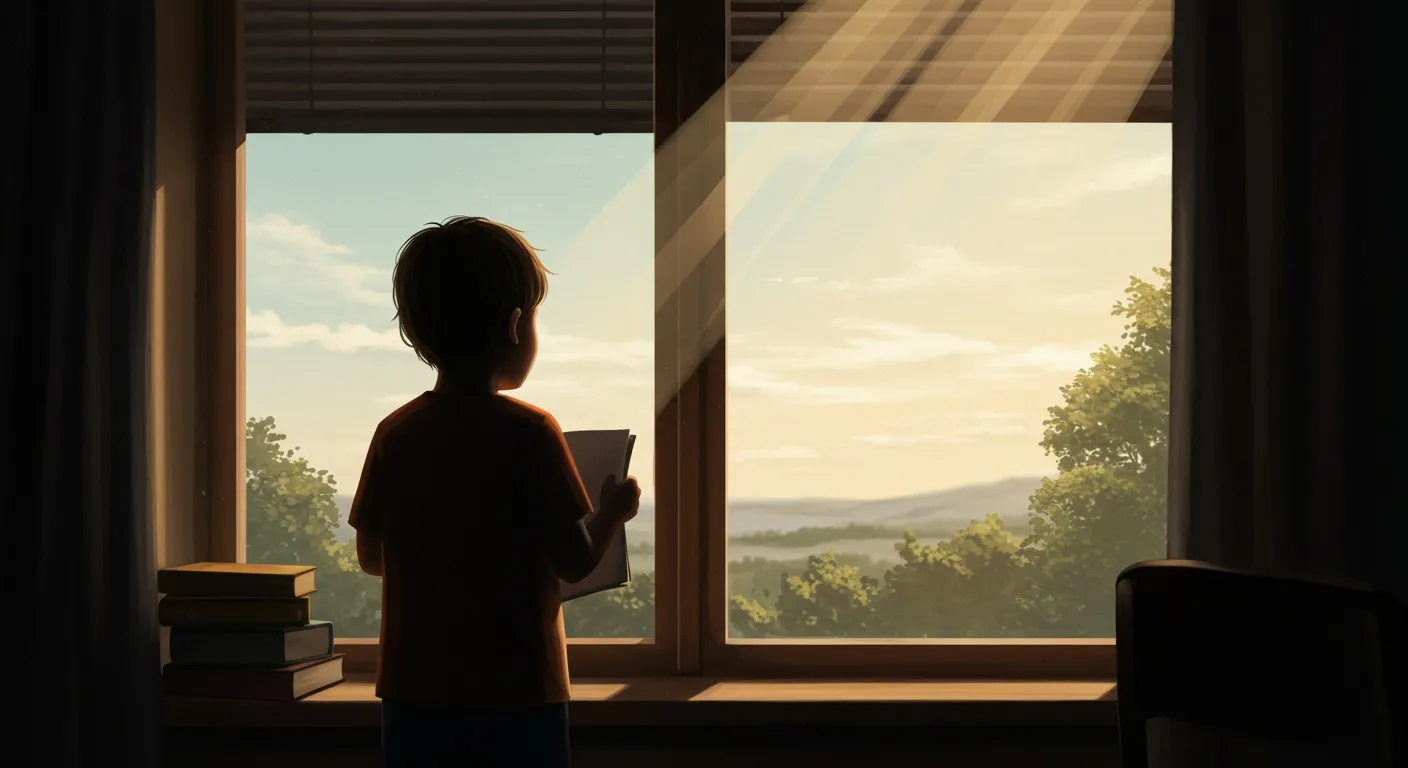子どもの視力低下が急増中!原因と家庭でできる近視予防法を眼科医が解説【2025年最新版】
2025/10/08
子供の視力低下が増加している現状
近年、子供の視力低下が深刻な問題となっています。文部科学省の令和2年度学校保健統計によると、裸眼視力1.0未満の子どもの割合は、幼稚園で27.90%、小学校で37.52%、中学校で58.29%、高等学校では63.17%にまで達しています。特に小学校・中学校では過去最多の割合となっているのです。
私が眼科医として診療していると、昔に比べて明らかに低年齢化が進んでいると感じます。以前は中学生から高校生の視力低下が主でしたが、今では小学校低学年、さらには就学前の子どもたちの視力低下も珍しくありません。
特に注目すべきは、視力低下の低年齢化です。6歳くらいの小学校入学時から近視が進行するケースが増えています。視力が悪くなると、黒板の文字が見えづらくなり学習に支障をきたしたり、スポーツでボールが見えにくくなったりと、子どもの生活全般に影響を及ぼします。
さらに深刻なのは、単に見えにくくなるだけでなく、将来的な目の健康リスクも高まることです。
日本眼科医会の調査によれば、軽度の近視であっても、近視がない場合と比較して緑内障になるリスクは4倍も高くなります。また、強度の近視に進行すると、網膜剥離などの重篤な眼疾患のリスクも上昇するのです。
子供の視力低下の主な原因
子供の視力低下、特に近視の原因には大きく分けて「遺伝要因」と「環境要因」があります。両親が近視である場合、子どもも近視になりやすい傾向があります。
しかし近年急増している子どもの視力低下の主な原因は、生活環境の変化によるものが大きいでしょう。特に以下の要因が大きく影響していると考えられます。
デジタル機器の長時間使用
スマートフォンやタブレット、ゲーム機などのデジタル機器の普及により、子どもたちが近くを見続ける時間が劇的に増加しています。
全国の眼科医を対象とした調査では、子どもの視力低下の原因として「スマートフォン・携帯ゲーム機」が49.3%と最も多く挙げられました。
長時間にわたって近くを見続けると、目の水晶体が膨らんだ状態が続き、眼球が前後方向に伸びてしまいます。これが近視の主な発生メカニズムです。
特に2025年現在、オンライン授業やデジタル教材の普及により、学校でも家庭でもスクリーンを見る時間が増えています。コロナ禍以降、デジタル化が一気に加速し、子どもたちの目への負担は以前にも増して大きくなっているのです。
屋外活動の減少
研究によれば、1日2~3時間の屋外活動(日陰でも可)をすることで、近視になるリスクが低くなることが報告されています。屋外の明るい光を浴びることで、ドーパミンという物質が分泌され、眼球の伸長を抑制する効果があるとされています。
しかし現代の子どもたちは、以前に比べて外で遊ぶ時間が大幅に減少しています。安全な遊び場の減少や、習い事の増加、そしてデジタル機器の普及により、屋内で過ごす時間が増えているのです。
自然光を浴びる機会が減ることで、目の健全な発達に必要な刺激が不足し、近視の進行を早めていると考えられます。
不適切な読書姿勢や照明環境
暗い場所での読書や、不適切な姿勢での長時間の近業作業も視力低下の原因となります。
適切な距離(30cm以上)を保たずに本や画面を見続けることで、目に過度な負担がかかるのです。
また、照明が不十分な環境での読書や学習も、目の疲労を引き起こし、視力低下につながります。
特に就寝前のスマートフォン使用は、ブルーライトの影響で睡眠の質を下げるだけでなく、目の健康にも悪影響を及ぼします。
視力低下が子供に与える影響
視力の低下は、子どもの日常生活や将来に様々な影響を及ぼします。
単に「見えにくい」という問題だけではなく、子どもの成長全体に関わる重要な問題なのです。
学習への影響
視力が低下すると、黒板の文字が見えづらくなり、正確な情報を読み取るのに時間がかかるようになります。これにより、授業の理解度が下がったり、学習効率が低下したりする可能性があります。 私の診療経験でも、「黒板が見えない」という理由で来院する子どもたちは少なくありません。視力の問題が解決されないまま放置されると、学習意欲の低下につながることもあります。特に2025年現在、デジタル教材やタブレットを使った授業が増えている中で、適切な視力矯正がなされていないと、デジタル機器の画面も見づらく、学習の遅れにつながる恐れがあります。
スポーツや日常活動への影響
視力低下は、スポーツ活動にも大きな影響を与えます。ボールが見えにくい、距離感がつかみづらいといった問題が生じ、運動能力の発揮を妨げることがあります。
また、友達と遊ぶ際にも、視力が悪いことでストレスを感じたり、自信を失ったりすることがあります。これが子どもの社会性や心理的発達にも影響を及ぼす可能性があるのです。
将来的な健康リスク
子どもの頃から進行する近視は、将来的な眼の健康リスクを高めます。特に強度近視(-6.0D以上)に進行すると、網膜剥離や緑内障、黄斑変性症などの深刻な眼疾患のリスクが大幅に上昇します。
日本眼科医会の資料によれば、軽度の近視であっても、近視がない場合と比較して緑内障になるリスクは4倍も高くなります。近視の度数が上がるほど、このリスクはさらに高まるのです。
人生100年時代と言われる今、子どもたちが生涯にわたって良好な視力を維持するためには、小児期の近視予防と進行抑制が非常に重要なのです。
効果的な視力低下予防策
子どもの視力低下を防ぐためには、日常生活での適切な対策が重要です。以下に、眼科医として特に効果的だと考える予防策をご紹介します。
20-20-20ルールの実践
デジタル機器を使用する際は、「20-20-20ルール」を実践しましょう。これは、20分ごとに、20フィート(約6メートル)先を、20秒間見るというルールです。
近くを見続けることによる目の疲労を軽減し、水晶体の緊張をほぐす効果があります。子どもにもわかりやすく説明し、タイマーを設定するなどして習慣づけるとよいでしょう。
私の患者さんの中には、このシンプルなルールを家族全員で実践することで、子どもの視力低下のスピードが緩やかになったケースもあります。特に長時間のオンライン授業や宿題の際には、意識的に休憩を取ることが大切です。
屋外活動時間の確保
1日2時間以上の屋外活動は、近視の予防に非常に効果的です。明るい自然光を浴びることで、ドーパミンの分泌が促され、眼球の過度な成長を抑制する効果があります。
週末には公園や自然の中で過ごす時間を意識的に作りましょう。スポーツや散歩など、外で体を動かす習慣をつけることは、視力保護だけでなく、全身の健康にも良い影響を与えます。
ただし、紫外線対策は忘れずに行いましょう。特に夏場の直射日光は、網膜や黄斑に影響を及ぼしたり、白内障の原因になる場合があります。帽子をかぶる、サングラスをかけるなどの対策が必要です。
適切な読書・学習環境の整備
読書や勉強をする際は、適切な距離(30cm以上)を保ち、正しい姿勢を心がけましょう。
また、十分な明るさを確保することも重要です。
デスクライトは、手元を明るく照らし、まぶしさを感じないものを選びましょう。
部屋全体も適度に明るくし、画面と周囲の明るさの差が大きくならないよう配慮することが大切です。
また、デジタル機器の画面の明るさや角度も適切に調整し、反射や映り込みが少なくなるよう工夫しましょう。長時間使用する場合は、ブルーライトカット機能を活用するのも一つの方法です。
デジタル機器の使用時間管理
子どものデジタル機器の使用時間を適切に管理することも重要です。年齢に応じた適切な使用時間の目安を設け、特に就寝前の使用は控えるようにしましょう。
私がお勧めしているのは、「デジタル機器を使う時間」と「使わない時間」をはっきり分けることです。例えば、食事中や就寝前1時間はデジタル機器を使わないなど、家族でルールを決めると効果的です。
また、デジタル機器の使用と屋外活動をバランスよく取り入れる工夫も大切です。「1時間ゲームをしたら、30分は外で遊ぶ」といったルールを設けるのも良いでしょう。
近視進行を抑制する最新治療法
子どもの近視が進行してしまった場合でも、その進行を抑制する効果的な治療法が近年開発されています。
2025年現在、日本で利用可能な主な治療法をご紹介します。
低濃度アトロピン点眼薬
2024年12月末に、日本でも初めて近視進行抑制治療として厚生労働省に承認された「リジュセアミニ点眼液0.025%」が2025年春から販売されています。
この点眼薬は、アトロピンという成分を低濃度で含んでおり、近視の進行を抑制する効果があります。
従来の高濃度アトロピンは副作用が強く日常的な使用は困難でしたが、低濃度にすることで副作用を軽減しつつ、効果を維持することに成功しました。
寝る前に1回点眼するだけで効果があり、治験では3年間にわたって近視進行抑制効果が持続することが確認されています。
この治療は4歳から15歳くらいまでの子どもに適しており、特に近視の進行が早い子どもに効果的です。
ただし、自由診療となる為、公的医療保険は適用されず、検査代も含めた全額が患者負担となる点に注意が必要です。
近視管理用眼鏡
近視の進行を抑制するために設計された特殊な眼鏡も選択肢の一つです。これらの眼鏡は、周辺部の網膜に特殊な光学的刺激を与えることで、眼球の伸長を抑制する効果があります。
通常の眼鏡やコンタクトレンズと比較して、装用開始から2年間で約55~60%近視の進行を抑制することが報告されています。眼鏡による治療なので、小さな子どもでも比較的簡単に実施できる利点があります。
特に低年齢の子どもや、コンタクトレンズの装用が難しい子どもには、この方法がお勧めです。日常生活に支障なく使用でき、副作用のリスクも低いのが特徴です。
多焦点ソフトコンタクトレンズ
多焦点ソフトコンタクトレンズも、近視進行抑制に効果があることがわかっています。
特にMiSight®1dayは、装用開始から3年間で近視進行を59%抑制することが示されており、日本でも承認された為、近日発売が予定されています。1日使い捨てタイプなので衛生面での管理が比較的容易ですが、自分で取り外しができる年齢になってからの使用が望ましいため、比較的年齢が高い小児が対象となります。
コンタクトレンズの管理や装着が適切にできることが前提となるため、お子さんの性格や生活習慣も考慮して検討する必要があります。
オルソケラトロジー
オルソケラトロジーは、特殊なハードコンタクトレンズを就寝時に装着し、角膜の形状を一時的に変化させることで、日中は裸眼で過ごせるようにする方法です。
近視矯正効果に加えて、装用開始2年間で近視進行を約32~63%抑制する効果も報告されています。夜間に大人の管理のもとで装用できるため、年齢の低い子どもでも選択されることがあります。
ただし、適切な処方や管理を怠ると角膜感染症など重篤な合併症を起こす可能性もあるため、専門医の指導のもとで正しく使用することが非常に重要です。
子供の視力チェックと眼科受診のタイミング
子どもの視力低下を早期に発見し、適切に対処するためには、定期的な視力チェックと適切なタイミングでの眼科受診が重要です。
家庭でできる視力チェック
家庭でも簡単な視力チェックを行うことができます。インターネットで視力検査表を印刷し、適切な距離から見えるかどうかを確認する方法があります。
ただし、これはあくまで目安であり、正確な検査ではないことを理解しておきましょう。
また、日常生活での子どもの様子を観察することも重要です。テレビに近づいて見る、目を細めて物を見る、頭を傾けて見る、すぐに目を擦るなどの行動が見られたら、視力に問題がある可能性があります。
小さなお子さんは自分から「見えにくい」と訴えることが少ないため、保護者の方の観察が特に大切です。
少しでも気になることがあれば、早めに眼科を受診しましょう。
学校の視力検査の活用
学校で行われる定期健康診断の視力検査結果は、視力低下の早期発見に役立ちます。
視力検査でB(0.7以下)と判定された場合は、眼科受診をお勧めします。
学校からの受診勧告があった場合は、できるだけ早く眼科を受診しましょう。視力低下の原因を特定し、適切な対応をすることで、進行を抑えられる可能性があります。
また、視力検査の結果が良好でも、お子さんが「黒板が見えにくい」などと訴える場合は、眼科を受診することをお勧めします。
学校の視力検査では発見できない問題が隠れている可能性もあります。
眼科受診が必要なサイン
以下のようなサインが見られたら、眼科受診を検討しましょう
・目を細めて物を見る
・テレビやスマートフォンに異常に近づく
・頭痛や目の疲れを頻繁に訴える
・目を頻繁にこする
・まぶしがる、または暗い場所を好む
・読書や勉強中に集中力が続かない
・視力検査でB判定(0.7以下)が出た
特に、両親が近視である場合や、デジタル機器の使用時間が長い子どもは、定期的な眼科検診をお勧めします。
早期発見・早期対応が、視力低下の進行を抑える鍵となります。
私の臨床経験では、小学校入学前に一度眼科検診を受けておくことで、潜在的な視力の問題を早期に発見できるケースが多くあります。
その後も、少なくとも年に1回は眼科検診を受けることをお勧めします。
まとめ:子供の視力を守るために今日からできること
子どもの視力低下は、適切な予防策と早期対応によって防ぐことができます。最後に、今日から実践できる具体的な対策をまとめてご紹介します。
まず、デジタル機器の使用時間を適切に管理し、20-20-20ルール(20分ごとに、20フィート先を、20秒間見る)を実践しましょう。また、1日2時間以上の屋外活動を確保することも非常に効果的です。
読書や勉強をする際は、適切な距離(30cm以上)と姿勢を保ち、十分な明るさを確保することが重要です。デジタル機器の画面の明るさや角度も適切に調整しましょう。
定期的な視力チェックと、必要に応じた眼科受診も欠かせません。
視力検査でB判定(0.7以下)が出た場合や、気になるサインが見られた場合は、早めに眼科を受診しましょう。
近視が進行してしまった場合でも、低濃度アトロピン点眼薬や近視管理用眼鏡、多焦点ソフトコンタクトレンズ、オルソケラトロジーなど、進行を抑制する効果的な治療法があります。
専門医と相談しながら、お子さんに最適な方法を選びましょう。
子どもの視力は、将来の目の健康に大きく影響します。
特に成長期の視力低下は、将来的な眼疾患のリスクを高める可能性があります。
私たち大人が適切な環境を整え、子どもたちの目の健康を守っていくことが大切です。
目の健康に関する詳しい情報や、お子さんの視力でお悩みの方は、ぜひ専門の眼科医にご相談ください。
梅の木眼科クリニックでは、お子さんの目の健康を守るための適切なアドバイスと治療を提供しています。
子どもたちが生涯にわたって良好な視力を維持できるよう、今日から一緒に取り組んでいきましょう。
詳しい情報や診療についてのお問い合わせは、梅の木眼科クリニックまでお気軽にご連絡ください。
小さなお子様からご高齢の方まで、幅広い年齢層の患者様に対応し、一人ひとりに合った治療をご提案いたします。
【著者情報】熊谷悠太
日本眼科学会認定 眼科専門医
2003年 聖マリアンナ医科大学医学部卒業、聖マリアンナ医科大学病院眼科学教室入局
2009年 聖マリアンナ医科大学大学院博士課程修了、桜ヶ丘中央病院眼科部長
2016年 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院眼科主任医長
2019年 梅の木眼科クリニック開院